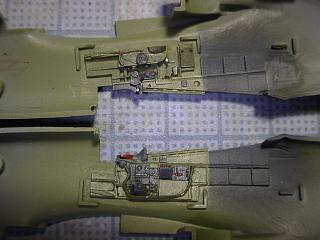|
今回は1/72ですが、Airesのセットを使ってコックピットの
ディーテールアップをします。キットの側壁モールドを削り落とし、
後でレジンパーツを接着したときに肉厚にならないよう、
さらに削り込んで薄くします。田宮のP-51Dキットは(1/72では1/48のように
透明部に直接ゲートをつけるということは
なくなったものの)キャノピーの処理が気に入らないので、ハセガワ用の
バキュームキャノピー(スコードロン製)を使うことにしました。
Futureでワックス処理済です。
ハセガワキットと同じように、ウインドシールドがつく部分のパネルを
後先考えず切り欠いてしまいました。
|
 |
画材店で最近購入したハンドバイスで、レジンの側壁パーツの
注入ブロックを保持し、サンドペーパーで肉を薄くしてやります。
この作業にはハンドバイスは必要なさそうですが、切り離しのときは
やりやすかったように思います。
|

 |
先ほど、胴体パーツから切り離した左右の計器盤覆いを接着し、
レジン製の計器盤パーツ(照準器も一体成形
されています)に接着してしまいました。以前使用したAiresの1/48
パーツでは、最初からこのような状態でした。照準器のレンズ部には、Polly-Scale
のクリア(フロアワックスのように半透明で、乾燥すると透明になります)
をたらしました(追記:塗料だと乾燥後
ひけてしまったので、クリスタルレジンでやり直しました)。
計器部は、エッチングパーツと
印刷した透明フィルムで再現するようになっています。
レジンとエッチングを適材適所で使い分けて、かつ値段も安価というのは
うれしいです。方向舵ペダルはエッチングです。こういう細かいエッチング
パーツを扱うのはストレスなので、キットのプラパーツを移植しようかとも
思いました(案の定、後でペダルがとれて付け直す羽目になりました)。
|
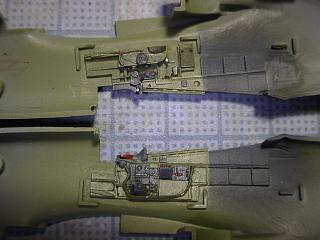 |
レジン製側壁パーツを接着し、エアロディーテール、Detail & Scale
を参考に塗りわけました。
|
 |
レジンの床パーツを接着します。合いはよいです。キットのコックピット
床パーツと一体成形されているラジエーターダクトを、バルクヘッドごと切り離して
使用しました。レジンの床パーツの後部は、ラジエータとダクトが収まるように
切り欠いてやります。
ラジエーターは塗装&スミ入れまでやって、マスキングしておきます。
後でマスキングテープをピンセットで挟んでつまみ出しやすいように、
タブを作っておきました。
|
 |
Airesのシートは、シートベルトやサイドステーがエッチングの別部品になって
いて面倒なので、全部レジンで一体成形されているTrue Detailsの
ものを使いました。Airesの方が出来上がりは上だったかもしれませんが、
作業の楽さをとってしまいました。また、Airesのシートの方が若干幅が
広めなので、側壁と干渉してしまうかもしれません。シートは最後に接着
するので、とりあえず塗装だけ済ませておきました。
|
 |
計器盤やシートはまだ接着せずに、全体塗装に備えて風防のみ
マットメディウムで仮接着しました。風防前部に隙間ができるので、
プラ板で埋めました。
|
 |
主翼と胴体の合いは悪くないですが、胴体の前方内側にランナーを
挟んでわずかに胴体幅を広げてやることにより、完璧に合うようになりました。
コックピットレジンパーツは片側の胴体にだけ接着し、遊びを持たせてあります。
主翼付け根の部分にプラペーパーを挟んだほうが、接着後に機首下面のラインが
スムーズにつながるようです。
|
 |
田宮の1/48キットから引き継がれている欠点ですが、プロペラカフスの
付け根が末広がりになり過ぎています。Czech Masterのレジンパーツを
参考にしつつ、削り込みました。
|
 |
塗装が終了しました。胴体のみ、控えめに銀のトーンを変えて塗り分けました。ベースの銀はアルクラッドのアルミを使いました。バキュームキャノピーを閉状態に削り合わせるのに若干苦労しました。
|

 |
完成です。マーキングは370FS/359FGのエースR.Wetmore機にしました。ホイールのみCzech Masterのレジン製自重変形状態のものを使用しています。田宮だからと仮組みをしなかったら、脚周りの組み立てにちょっと苦労しました。内側の脚カバーの支柱が若干長すぎて、そのままでは角度が決まりません。クリアパーツの着陸灯は、レンズ部分をリューターでえぐって、カーモデル用のライトを埋め込みました。エアロマスターデカールのインストでは、スピナーに白のスパイラルが描かれていますが、実機の写真には確認できないので省略しました。1/72の単発機は小さいですね。
|